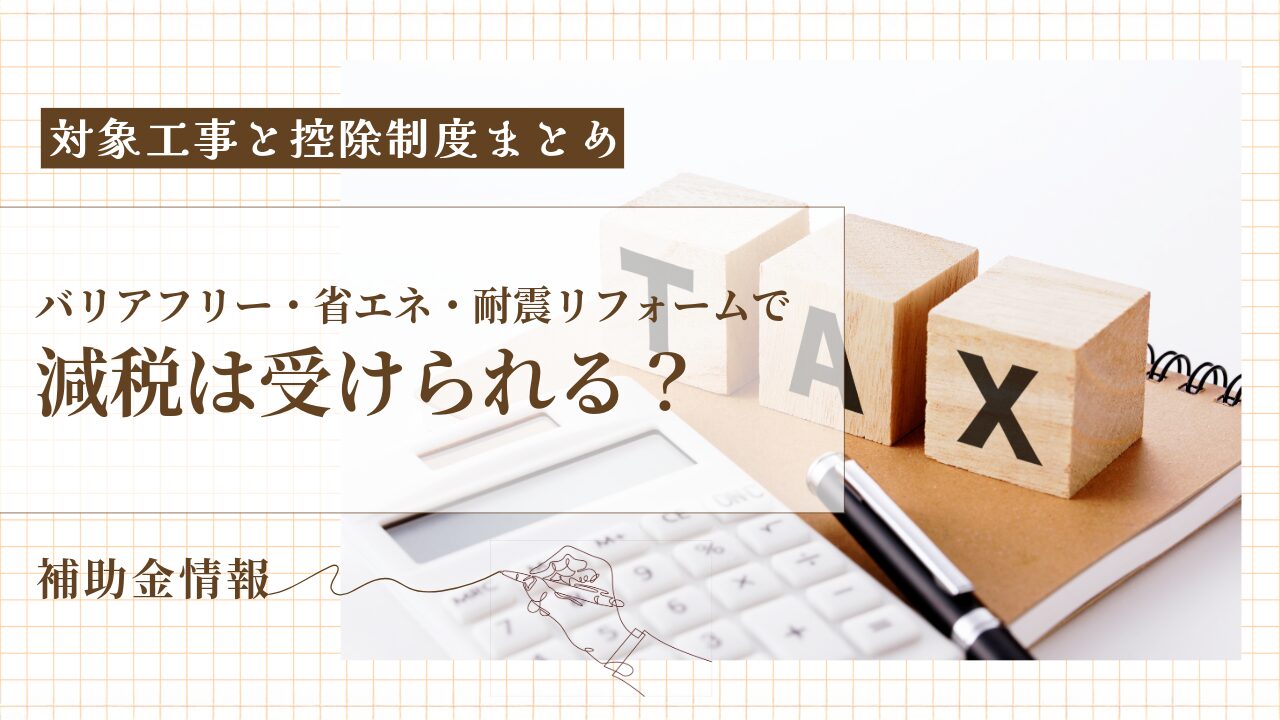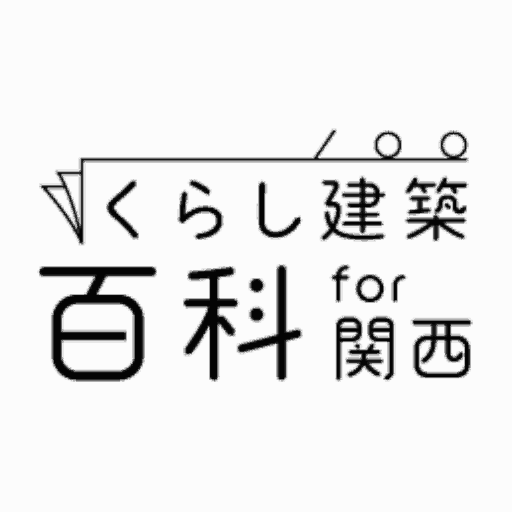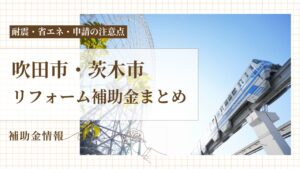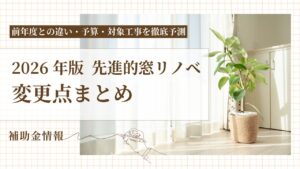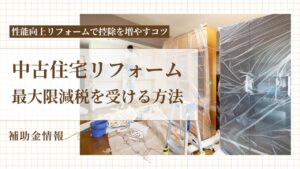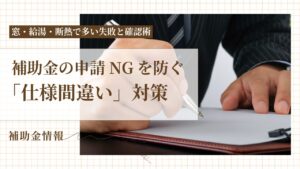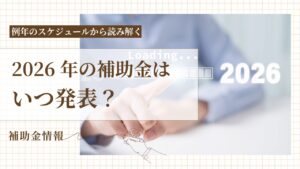はじめに
リフォームを検討する際、「工事費を少しでも抑えたい」「減税や控除が受けられるなら利用したい」と考える方は多いでしょう。
実は、国が推進するバリアフリー化、省エネ改修、耐震改修といったリフォームは、特定の条件を満たせば所得税や固定資産税の減税制度が利用できます。
しかし「どの工事でどんな減税が受けられるのか」がわかりにくいのも事実。
この記事では、工事ごとに適用される減税制度をわかりやすくまとめ、リフォームを計画する際に役立つ情報を整理しました。
リフォーム減税の種類
リフォーム減税は大きく分けて次の3種類があります。
| 減税の種類 | 内容 | 代表的な制度 |
|---|---|---|
| 所得税の控除 | 確定申告で税金が戻る | 住宅ローン減税、投資型減税 |
| 固定資産税の減額 | 翌年度の固定資産税が軽減 | バリアフリー・省エネ改修など |
| 贈与税・相続税の非課税 | 親や祖父母から資金を援助された場合に非課税枠拡大 | 住宅取得等資金贈与の特例 |
ここからは、工事別にどの制度が使えるかを具体的に解説します。
バリアフリーリフォームと減税制度

高齢化社会を背景に、バリアフリー改修は国が積極的に支援している分野です。
対象となる工事例
- 手すりの設置
- 段差の解消(スロープ設置・床の段差解消)
- 廊下幅や出入口の拡張
- トイレや浴室の改修(高齢者対応)
使える減税制度
| 減税制度 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 所得税控除(住宅ローン減税 or 投資型減税) | 工事費の一部が所得税から控除 | 工事費50万円以上など |
| 固定資産税の減額 | 翌年度の固定資産税が1/3減額 | 工事費30万円以上、一定の居住要件 |
高齢者と同居する予定がある家庭や、将来を見据えた住まいづくりにはバリアフリー改修+減税制度の活用が有効です。
省エネリフォームと減税制度

エネルギー価格高騰や脱炭素社会に向け、省エネリフォームの需要も増えています。
対象となる工事例
- 窓の断熱改修(二重サッシ・断熱ガラス)
- 外壁・屋根・天井・床の断熱工事
- 高効率給湯器(エコジョーズ・エコキュート)への交換
- 太陽光発電・蓄電池の導入
使える減税制度
| 減税制度 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 所得税控除(投資型減税) | 工事費用の10%が所得税控除 | 工事費60万円以上など |
| 固定資産税の減額 | 翌年度の固定資産税が1/3減額 | 窓改修、断熱工事など |
| 住宅ローン減税 | ローンを利用して工事した場合に利用可 | 100万円以上の工事が対象 |
断熱や設備更新の省エネリフォームは「光熱費削減+減税」でダブルのメリットがあります。
耐震リフォームと減税制度

南海トラフ地震など大規模災害に備え、耐震化は特に注目されています。
対象となる工事例
- 木造住宅の耐震補強(壁・基礎・屋根の補強)
- シェルターや制震装置の設置
- 耐震診断に基づいた耐震改修
使える減税制度
| 減税制度 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| 所得税控除(特定耐震改修特別控除) | 工事費用の10%を控除 | 工事費25万円以上、1981年5月以前建築など |
| 固定資産税の減額 | 翌年度の固定資産税を1/2減額 | 耐震改修により新耐震基準を満たすこと |
| 住宅ローン減税 | 耐震工事に伴うローンも対象 | 工事費100万円以上 |
和歌山・南海沿岸地域など地震リスクの高いエリアでは、耐震改修と減税制度を組み合わせて「安心+節税」を実現するのが賢い選択です。
工事と減税制度の対応表まとめ

最後に、主要なリフォーム工事と減税制度の関係を一覧表に整理しました。
| 工事の種類 | 所得税控除 | 固定資産税減額 | ローン減税 |
|---|---|---|---|
| バリアフリー改修 | 〇(工事費50万以上) | 〇(翌年度1/3減額) | △(条件により) |
| 省エネ改修 | 〇(工事費60万以上) | 〇(窓改修などで1/3減額) | 〇(100万円以上) |
| 耐震改修 | 〇(工事費25万以上、旧耐震建物) | 〇(翌年度1/2減額) | 〇(100万円以上) |
減税を受けるための注意点
- 事前に制度の条件を確認すること
年度ごとに条件が変わる場合があるため、国土交通省や自治体の公式ページで最新情報を確認しましょう。 - 申請には書類が必要
工事証明書、領収書、住宅の登記事項証明書などを揃える必要があります。 - 信頼できる工務店に依頼すること
減税対象工事かどうかを理解している工務店なら、証明書の発行や申請サポートもスムーズです。
まとめ
- バリアフリー、省エネ、耐震といったリフォームは減税制度が充実している
- 所得税控除、固定資産税減額、住宅ローン減税が代表的な制度
- 減税を受けるには工事内容・金額・対象条件を満たす必要がある
特に共働き世代や子育て世代にとって、減税を活用すれば将来に備えたリフォームを実質的に安く実現できる可能性があります。
ただし、制度は複雑で申請手続きも煩雑になりがち。信頼できる地元工務店に相談することが、安心して減税を受けるための第一歩です。