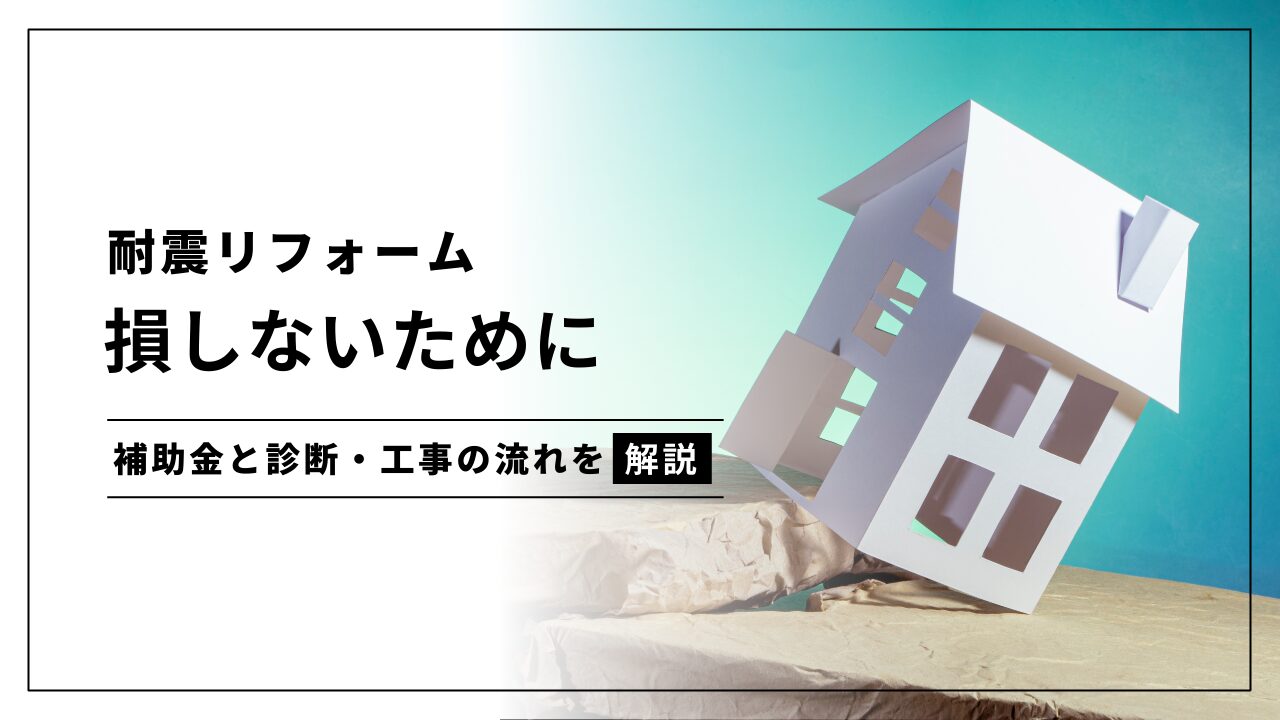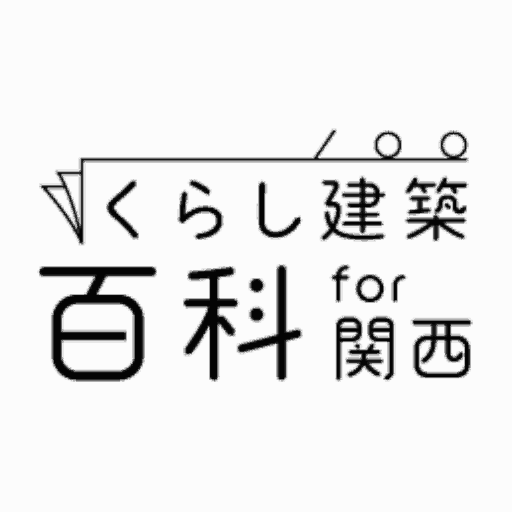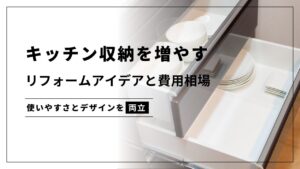目次
はじめに
日本は地震大国であり、住宅の耐震性は安心して暮らすための最重要ポイントです。
特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、震度6以上の地震で倒壊リスクが高いとされており、耐震診断・耐震リフォームは命と財産を守る投資といえます。
一方で、耐震リフォームは数百万円規模になることも多く、補助金や減税制度をうまく活用することが欠かせません。
本記事では、耐震リフォームの流れと補助制度の活用法を詳しく解説します。
関連記事:リフォーム減税と固定資産税減額制度の違いと活用法【2025年版】
耐震リフォームが必要となる住宅

- 旧耐震基準(1981年5月以前)で建築された木造住宅
- 築年数が古く、壁量不足や基礎のひび割れが見られる住宅
- 屋根が重い瓦屋根で、地震時に倒壊リスクが高い住宅
耐震リフォームの流れ
ステップ1:耐震診断
専門の建築士が構造を調査し、倒壊の危険度を判定。
ステップ2:補強計画の作成
壁の追加、基礎補強、屋根の軽量化などを組み合わせた計画を立案。
ステップ3:工事の実施
計画に基づいて補強工事を実施。工期は内容により1〜3か月。
ステップ4:補助金申請・完了報告
補助金は「診断→計画→工事」それぞれに制度が分かれるケースがあり、段階的に申請が必要。
耐震リフォームの工事内容と費用目安

| 工事内容 | 費用相場 | 工期目安 |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 5〜15万円 | 約1日 |
| 壁の補強(耐力壁追加) | 50〜150万円 | 1〜2週間 |
| 基礎補強(鉄筋コンクリート巻き立て) | 100〜250万円 | 2〜4週間 |
| 屋根の軽量化(瓦→金属屋根) | 100〜200万円 | 2〜3週間 |
| 全面的な耐震改修 | 200〜500万円 | 1〜3か月 |
関連記事:相場より高い?安い?工事別リフォーム費用の目安まとめ
耐震リフォームで活用できる補助制度
国の制度:こどもエコ住まい支援事業
- 省エネ改修と併せて耐震性向上を行う場合、補助対象になるケースあり
- 子育て世帯・若者夫婦世帯であれば、他の工事と組み合わせることでさらに補助額が増える
自治体の制度
- 大阪市:木造住宅耐震改修に最大120万円の補助
- 尼崎市・西宮市:耐震改修に加え、外壁・屋根改修も対象
- 京都市:京町家の耐震補強を含む修景改修に助成
関連記事:【大阪市】外壁塗装・耐震補強などに使える2025年度補助制度ガイド
関連記事:尼崎市・西宮市のリフォーム助成金ガイド|兵庫県内の制度比較
補助金と減税制度の違い
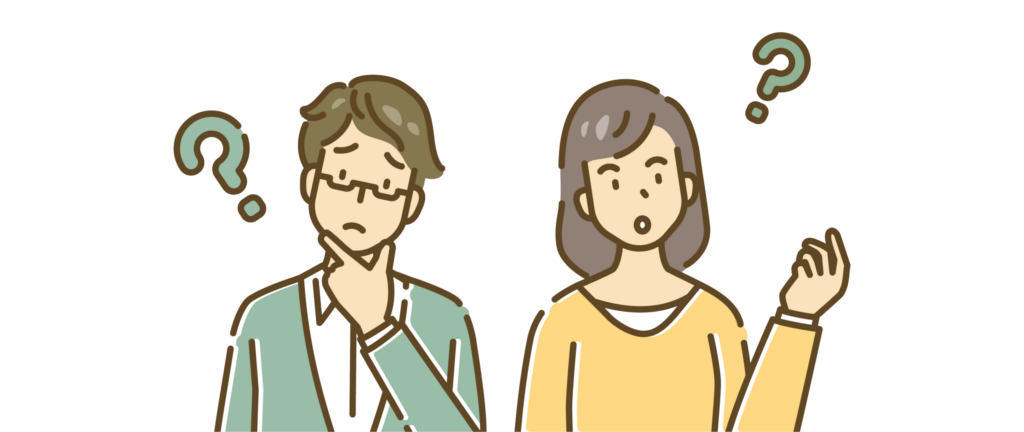
| 制度 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 補助金 | 工事費用の一部を国や自治体が助成 | 予算枠があり早めの申請が必要 |
| 減税制度 | 所得税・固定資産税の控除 | 確定申告で申請、併用可能 |
関連記事:リフォーム減税でいくら戻る?固定資産税/所得税の控除制度をわかりやすく解説
トラブルを避けるための注意点
- 工事前に補助対象かを必ず確認
→ 工務店が登録事業者かどうかを確認する。 - 契約書に処分費・追加工事費を明記
→ 曖昧な契約はトラブルの原因。
関連記事:曖昧な契約書が原因でトラブルに?工務店との契約でありがちな失敗 - 工期に余裕を持つ
→ 耐震工事は天候や建物状況により遅延しやすい。
まとめ

- 耐震リフォームは「診断→計画→工事」の流れで進める
- 工事費用は数十万〜数百万円規模で、補助金や減税制度を併用すれば大幅に負担軽減できる
- 国の「こどもエコ住まい支援事業」や自治体独自の制度を必ずチェックする
- 契約前の確認と信頼できる工務店選びが、後悔しない耐震リフォームのカギ