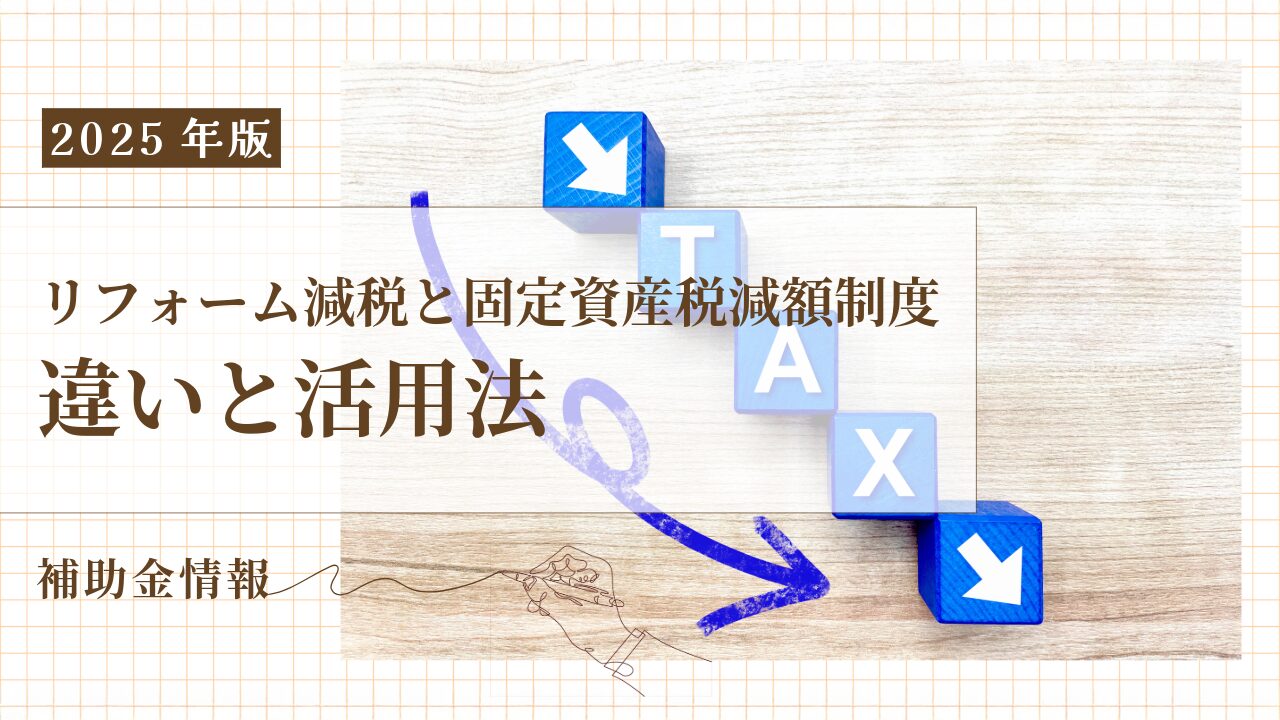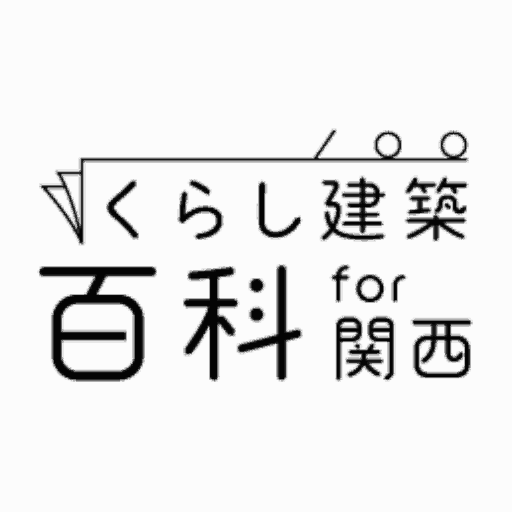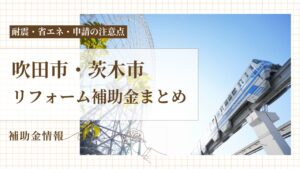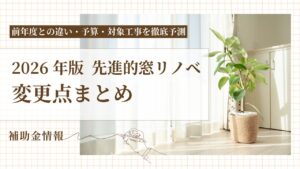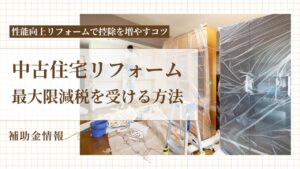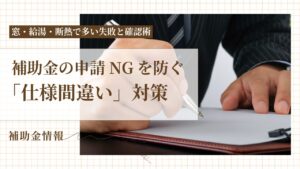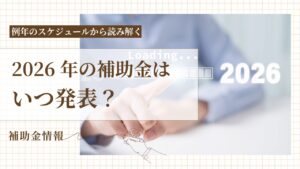目次
はじめに
リフォームを検討する際に気になるのが「税金の優遇制度」。
国や自治体ではさまざまな減税・控除制度を用意しており、上手に活用すれば大きな節税効果が期待できます。
しかし、「リフォーム減税」と「固定資産税減額制度」の違いが分かりにくく、どちらをどう使えばよいのか迷う方も多いでしょう。
本記事では、この2つの制度の違いを整理し、具体的な活用方法をわかりやすく解説します。
関連記事:バリアフリー・省エネ・耐震リフォームで減税は受けられる?対象工事と控除制度まとめ
リフォーム減税とは?

概要
「リフォーム減税」とは、特定のリフォーム工事を行った際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
国税庁が定める対象工事を行い、確定申告を通じて減税を受ける仕組みです。
主な対象工事
- バリアフリー改修
- 省エネ改修(断熱・窓・高効率設備)
- 耐震改修
- 住宅ローンを利用した増改築
減税の種類
- 所得税控除(固定額または一定率控除)
- 住宅ローン減税(最大13年の控除)
固定資産税減額制度とは?

概要
固定資産税減額制度は、リフォーム後の建物にかかる固定資産税が軽減される仕組みです。
通常、リフォームで住宅の価値が上がると固定資産税も増加しますが、一定条件を満たす工事では減額措置が受けられます。
主な対象工事
- 耐震改修
- バリアフリー改修
- 省エネ改修
減額内容
- 改修後3年度分(最大)にわたり、固定資産税を1/2に減額
- 工事内容・規模により上限あり
リフォーム減税と固定資産税減額制度の違い(比較表)
| 項目 | リフォーム減税 | 固定資産税減額制度 |
|---|---|---|
| 減税対象 | 所得税・住民税 | 固定資産税 |
| 手続き方法 | 確定申告 | 市区町村への申請 |
| 対象工事 | バリアフリー、省エネ、耐震など | 耐震、省エネ、バリアフリー |
| 効果 | 所得税額の控除・還付 | 固定資産税の軽減 |
| 期間 | 1年〜住宅ローン減税で最大13年 | 最大3年度分 |
関連記事:審査に通らない?補助金申請で失敗しやすい3つの落とし穴
制度を活用する流れ
リフォーム減税の場合
- 工務店に対象工事かどうか確認
- 契約・工事を実施
- 工事証明書や領収書を保管
- 確定申告で控除申請
固定資産税減額制度の場合
- 工務店に対象工事か確認
- 工事着工前に市区町村へ事前相談
- 工事後に申請書類を提出
- 翌年度以降の固定資産税が減額
併用は可能?注意点

- リフォーム減税と固定資産税減額制度は併用可能ですが、同じ工事で二重に申請できない場合があります。
- 手続き窓口が「税務署」と「市区町村」で異なるため、両方の申請スケジュールを調整することが重要です。
制度を賢く使うためのポイント

| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 事前確認 | 工務店に「減税対象工事証明書」を発行してもらえるか確認 |
| 工期調整 | 工事完了から申告期限まで余裕を持つ |
| 書類管理 | 契約書・領収書・工事証明書を必ず保管 |
| 併用検討 | 減税と固定資産税減額を両立できるか確認 |
関連記事:相場より高い?安い?工事別リフォーム費用の目安まとめ【2025年版】
まとめ
- リフォーム減税は「所得税・住民税の控除」、固定資産税減額制度は「固定資産税の軽減」と対象が異なる
- どちらも耐震・省エネ・バリアフリー工事が中心だが、手続きや申請先が違う
- 併用も可能な場合があるため、工務店・税務署・市区町村に早めに相談するのがポイント
- 書類の不備や申請の遅れが大きなリスクになるので注意
リフォーム費用を少しでも抑えるには、減税制度と固定資産税減額制度を賢く活用することが重要です。